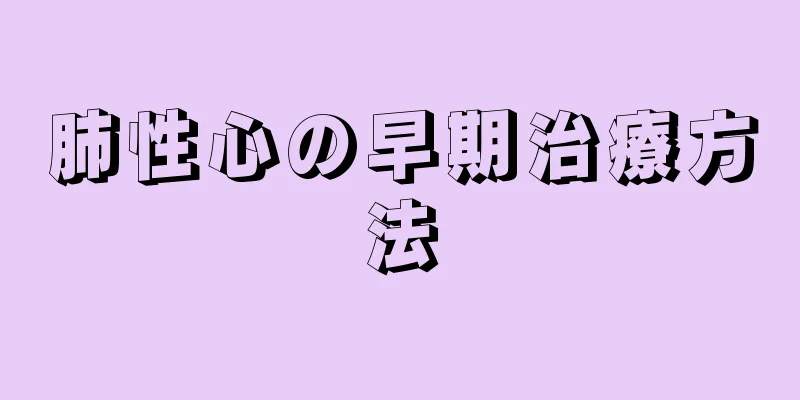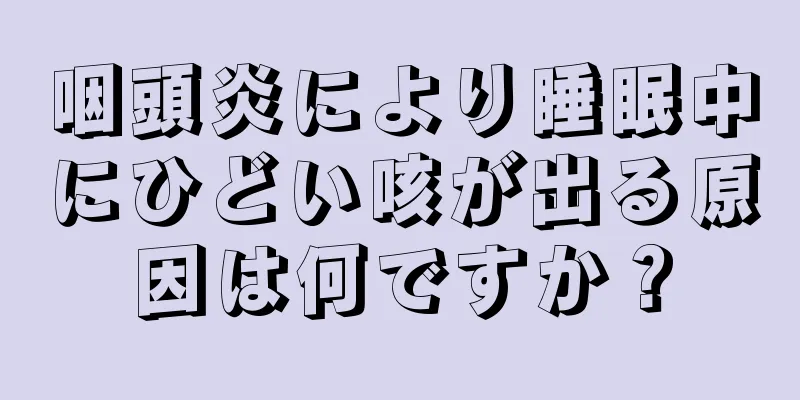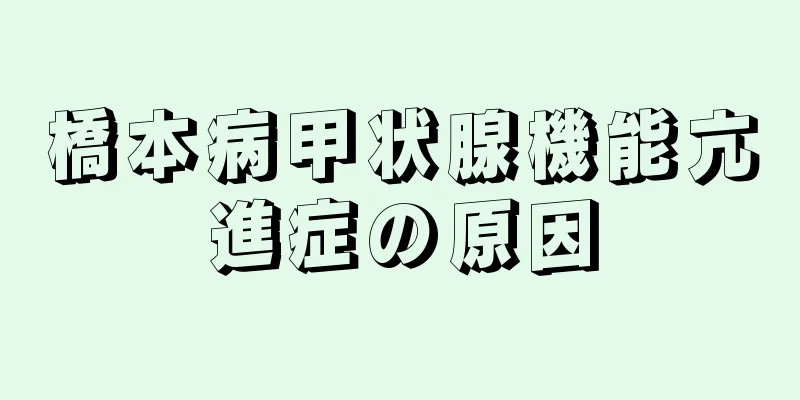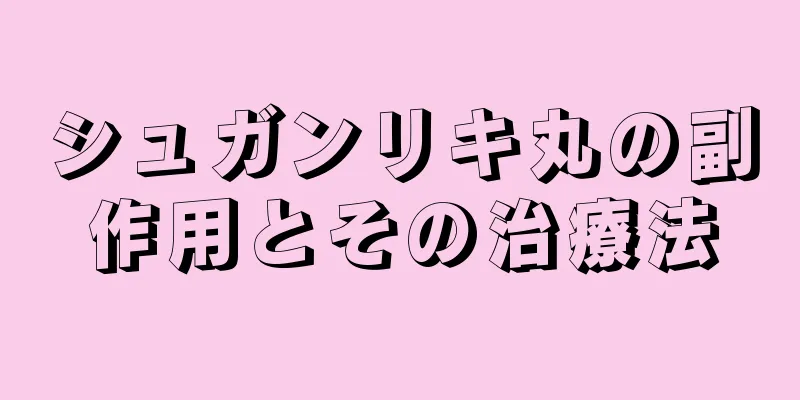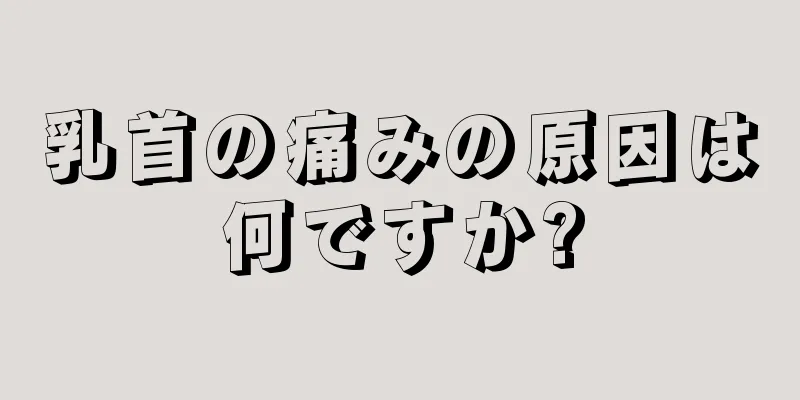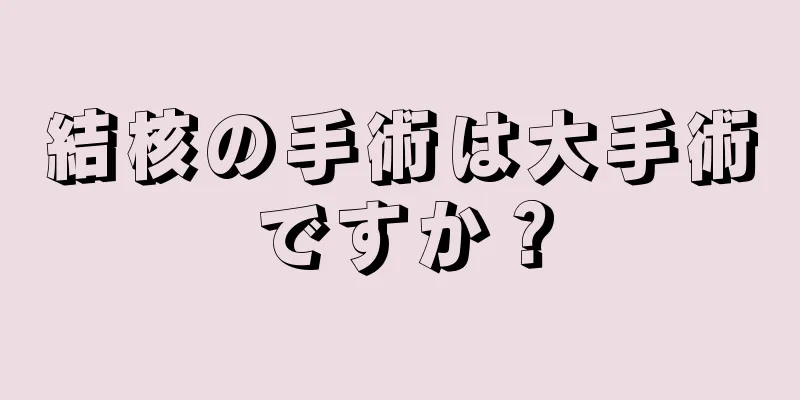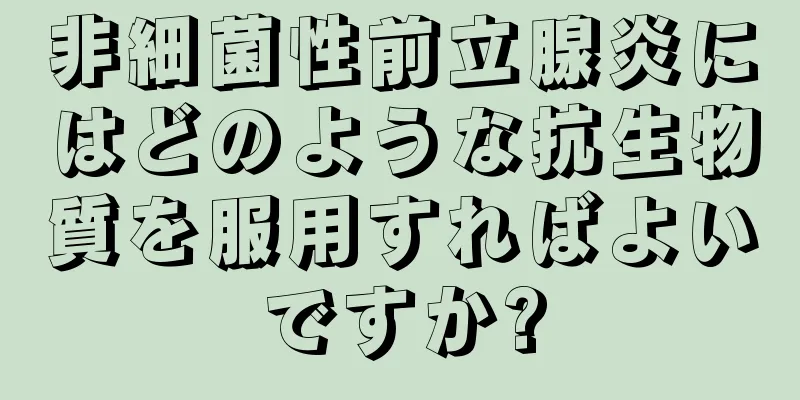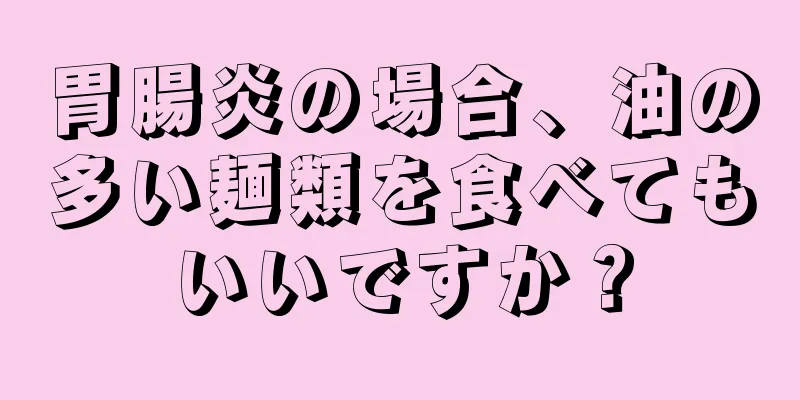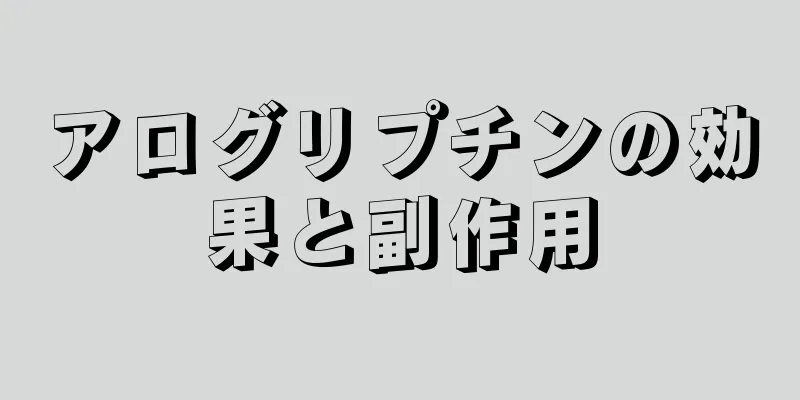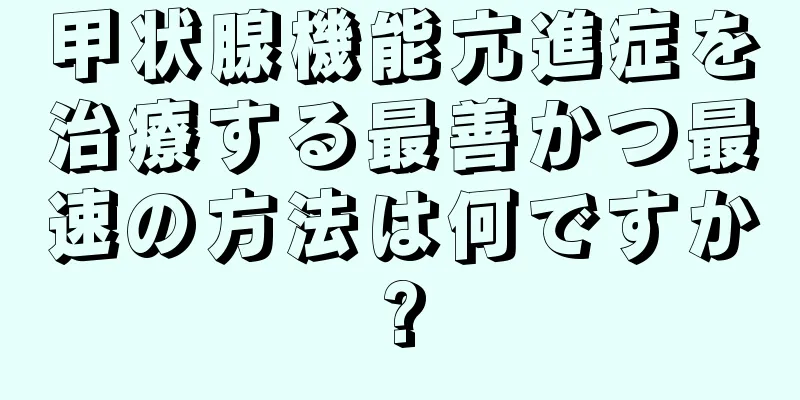赤ちゃんの便に粘液が含まれていると便秘になりますか?
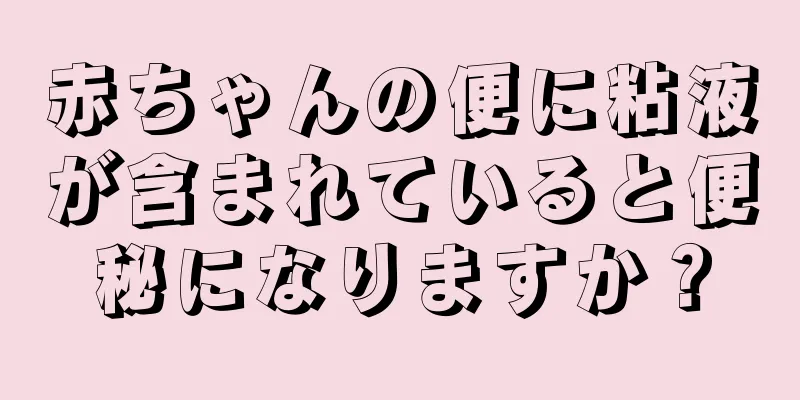
|
赤ちゃんの便に粘液が混じっている場合、便秘であるかどうかは、一般的に、赤ちゃんの便に粘液が混じっている理由に基づいて判断する必要があります。赤ちゃんの便に粘液が混じっている場合は、不適切な食事、腹部の冷え、腸内細菌叢の不均衡、または感染症が原因である可能性があります。明確な診断を得るために、早めに医師の診察を受けることをお勧めします。 1. 不適切な食事:赤ちゃんが日常生活で脂肪分の多い肉などの脂っこくて消化しにくい食べ物を多く食べると、赤ちゃんの便に含まれる脂肪分が多くなり、赤ちゃんの便に粘液が混じるようになります。通常、これによって赤ちゃんの便秘が起こることはありません。 2. お腹が冷たい:日常生活で赤ちゃんのお腹を暖かく保つことに注意を払わず、赤ちゃんのお腹が冷えてしまうと、胃腸機能障害を引き起こし、腸の蠕動運動が加速し、赤ちゃんに粘液便が出る原因になりますが、一般的には便秘を引き起こすことはありません。 3. 腸内細菌叢の不均衡:赤ちゃんの食事が不衛生な場合、腸内で病原菌が増殖し、腸粘膜の損傷、腸炎、腸内での水分の過剰吸収、軟便を引き起こす可能性があります。赤ちゃんの便は粘液便として現れますが、一般的には赤ちゃんに便秘を引き起こすことはありません。 4. 感染: 赤ちゃんがウイルスや細菌などの病原体に感染すると、病原体が胃腸粘膜に侵入し、胃腸機能障害を引き起こし、腸の運動性が高まり、便の性質が変化し、赤ちゃんの便に粘液が出ることがあります。いくつかの病原体も赤ちゃんの便秘を引き起こす可能性があります。 。 日常生活では、親は赤ちゃんの食品衛生に注意し、汚れた食べ物を食べさせないようにすることが推奨されます。赤ちゃんの便にひどい粘液が混じっている場合は、原因を突き止め、適切な検査を受けた後に対症療法を受けるために、両親は早めに赤ちゃんを医者に連れて行くことが推奨されます。 |
推薦する
膵炎の段階と危険性は何ですか?
膵炎の危険性は何ですか?膵炎の経過は一般的に3つの段階に分けられます。 1. 急性反応期は自然発生か...
糖尿病の顔面症状
糖尿病患者の顔の表情は多様であり、血糖値、微小血管疾患、神経障害などの要因に関連している可能性があり...
同舒生益丸が薬剤耐性を持つようになるまでどのくらいかかりますか?
同軒萬生丸は伝統的な中国薬として、風寒や肺気の停滞によって引き起こされる風邪や咳の治療に広く使用され...
貧血を治療しないと死んでしまうのでしょうか?
貧血を治療しないと死んでしまうのでしょうか?貧血が食生活の乱れや造血原料の異常などによって引き起こさ...
慢性細菌性赤痢の原因は何ですか?
慢性細菌性赤痢の主な原因は、治療の不完全さ、免疫機能の低下、反復感染、生活環境の悪さなどであり、根本...
腎嚢胞とは何ですか?
腎嚢胞とは、腎臓の内部に発生し、外界とつながっていない嚢胞性病変の総称です。一般的な腎嚢胞には、単純...
慢性骨髄性白血病を治療せずにどれくらい生きられるのでしょうか?
CML 患者が治療を受けずにどのくらい生存できるかを示す明確な臨床データはありません。一般的に、患者...
Selinexor の効果と機能は何ですか?
セリネクソルは、多発性骨髄腫および転座関連DLBCLと呼ばれるびまん性大細胞型B細胞リンパ腫のサブタ...
女性が吐き気、腰痛、下腹部痛を経験するのはなぜでしょうか?
女性が吐き気、腰痛、下腹部痛を経験するのはなぜでしょうか?女性の吐き気、腰痛、下腹部痛は、通常、生理...
銀橋結毒顆粒の副作用が起こったらどうすればいいですか?
銀橋結毒顆粒は、一般的に使用されている漢方薬製剤で、主に風熱風邪による発熱、頭痛、咳、口渇、喉の痛み...
風邪の咳と肺炎の咳の違いは何ですか?
風邪は一般的に上気道感染症を指します。上気道感染症による咳と肺炎による咳は、付随する症状、回復時間、...
白血病の10大警告サイン
白血病は血液と骨髄に影響を及ぼす悪性腫瘍です。初期症状は多岐にわたるため、真剣に受け止める必要があり...
天馬頭痛薬の有効期間はどのくらいですか?
天麻頭痛錠は、伝統的な漢方薬として、外因性の風寒、瘀血、または血虚や栄養失調によって引き起こされる偏...
心臓病の検査にはどのようなものがありますか?
心臓病の検査にはどのようなものがありますか?心臓病の検査には、血清心筋マーカー検査、脳性ナトリウム利...
洞性不整脈の予防策
洞性不整脈の注意事項:洞性不整脈に対する予防策としては、通常、水分を多く摂ること、消化しやすい食べ物...