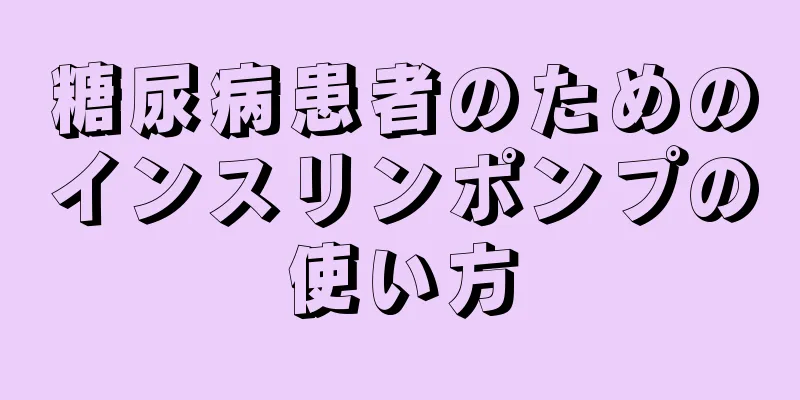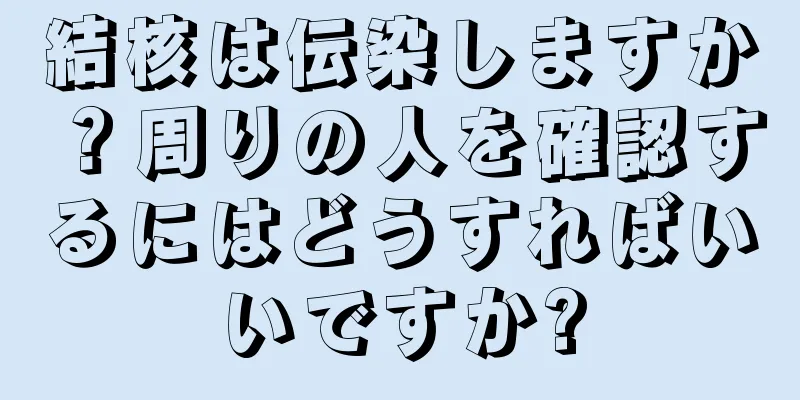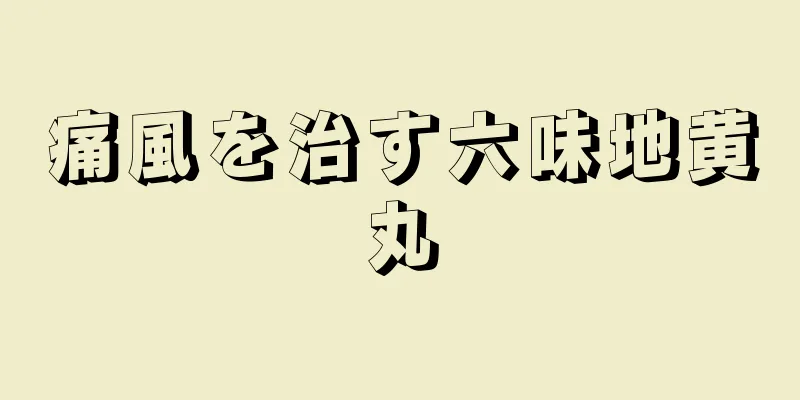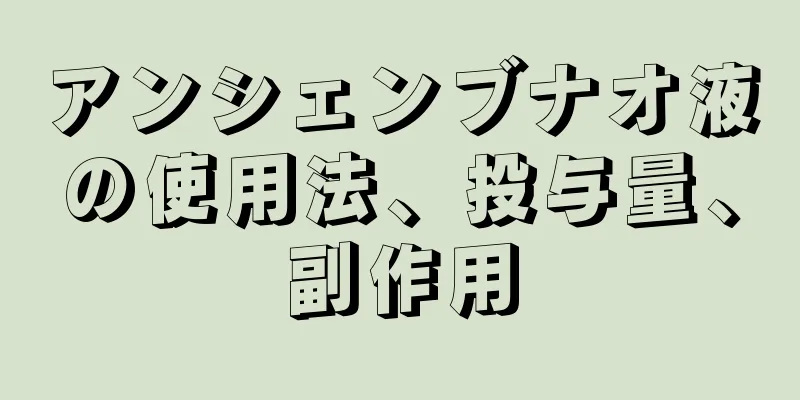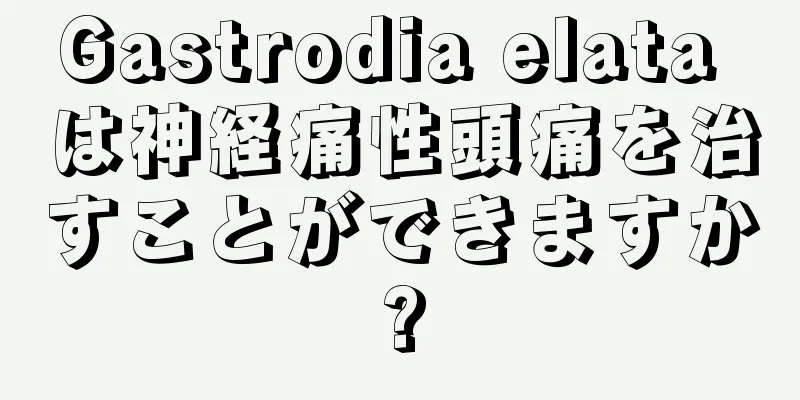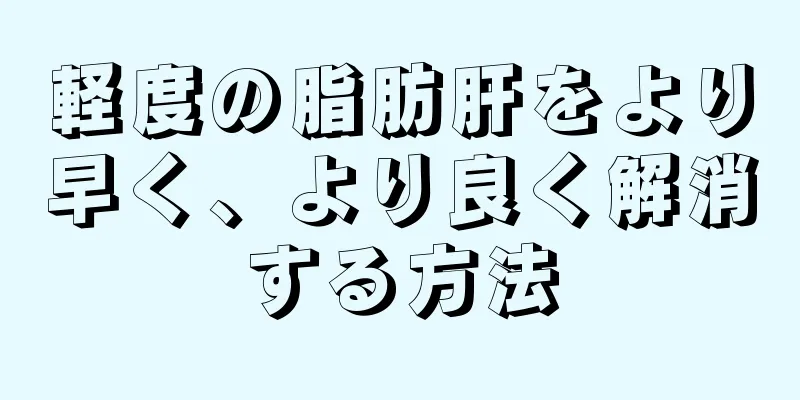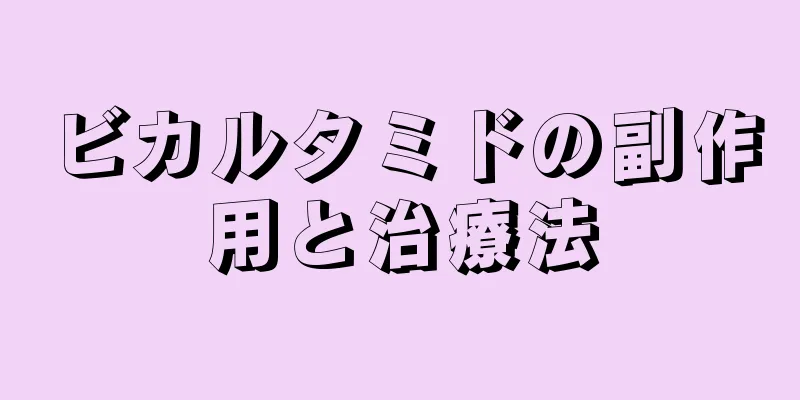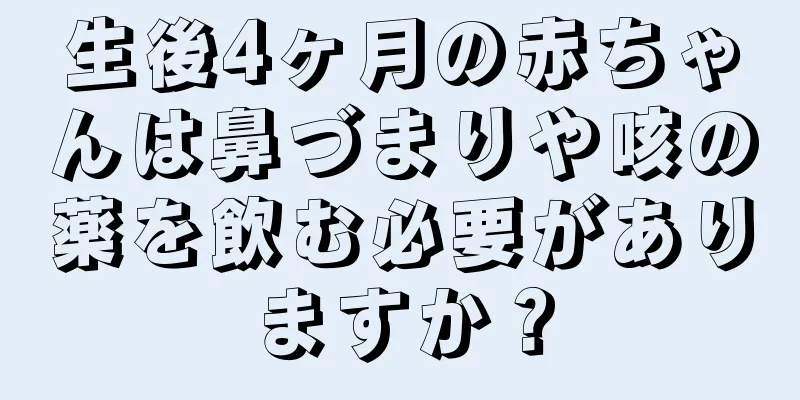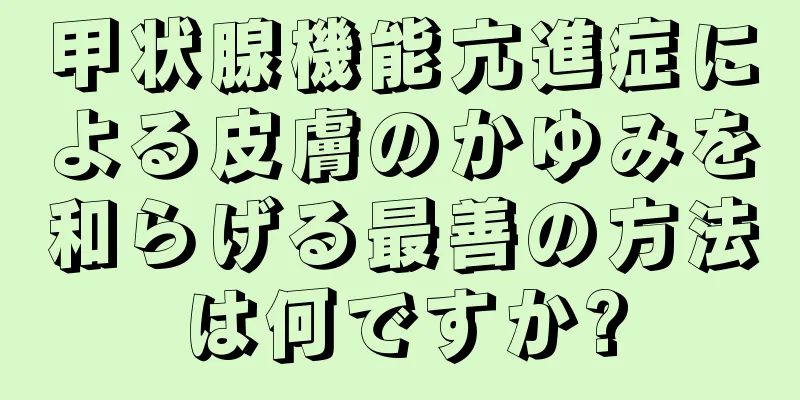オフロキサシン眼軟膏の使用方法と投与量
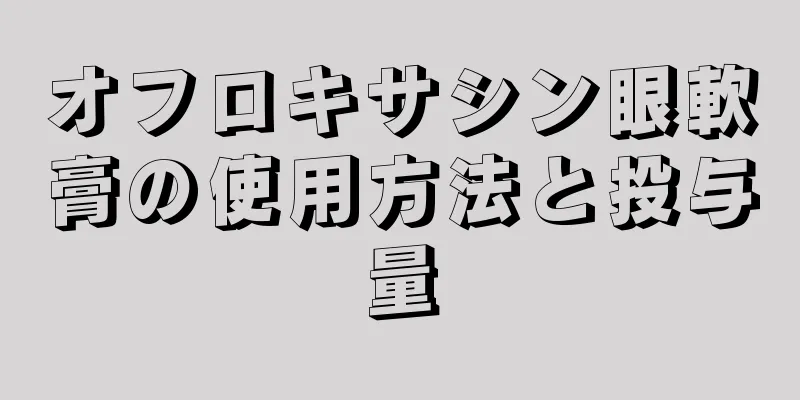
|
オフロキサシン眼軟膏は、眼感染症の治療によく使用される薬剤で、細菌性結膜炎、角膜炎、角膜潰瘍、涙嚢炎、術後感染症などの外眼感染症に特に適しています。次にオフロキサシン眼軟膏の使い方と用量について詳しく紹介します。 1. 用法・用量 オフロキサシン眼軟膏を使用する前に、手を洗い、目の衛生を確保してください。適量の眼軟膏を、米粒大くらいの量を取り、下まぶたの結膜嚢の中に押し出します。目を閉じて眼球をゆっくり回転させ、眼球の表面に軟膏を均一に広げます。使用後は薬剤の漏れを防ぐために1〜2分間目を閉じてください。他の点眼薬を同時に使用する必要がある場合は、使用前に15分待ってください。 2. 投薬時間 通常、1日3〜4回、1回につき米粒大を摂取してください。投薬期間は医師のアドバイスに基づいて決定され、一般的な治療期間は 7 ~ 10 日間です。症状が改善しない場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 3. タブー オフロキサシンにアレルギーのある患者には禁忌です。妊娠中の女性、授乳中の女性、子供、白内障患者、角膜損傷患者は注意して使用してください。使用中に不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。 4. 副作用 オフロキサシン眼軟膏の使用により、局所的な灼熱感、発赤、腫れ、かゆみ、結膜充血などの副作用が起こる可能性があります。重篤な副作用が起こった場合は、直ちに薬の服用を中止し、医師の診察を受けてください。 オフロキサシン眼軟膏は眼感染症の治療によく使われる薬ですが、副作用を避けるために使用時には用法・用量に注意し、医師の指導のもとで使用する必要があります。ご質問がある場合や体調が悪くなった場合は、すぐに医師の診察を受けてください。 |
推薦する
金時カプセルの適応症、注意事項および禁忌
金芎カプセルは、清熱解毒、脾臓強化除湿、経絡浚渫血循環促進などの効果を持つ、よく使われる漢方薬です。...
薬を飲んだ後にリウマチ因子が再び上昇するのはなぜですか?
関節リウマチの治療薬を服用している場合、リウマチ因子指数の上昇は不適切な投薬や病気の悪化に関係してい...
小児糖尿病には合併症がありますか?これら4つは非常に一般的です。
近年、糖尿病の発症率は比較的高くなっています。成人だけでなく、小児でも糖尿病患者は多く見られます。多...
インフルエンザウイルス肺炎の子供はどのような薬を服用すべきか
小児インフルエンザウイルス性肺炎は、抗ウイルス薬、抗生物質、咳止め薬、去痰薬で治療できます。親は早め...
子供が熱を出して突然てんかんのような症状になったら何が起きているのでしょうか?
子供が突然てんかんのような発熱を起こした場合、高熱によるけいれん、脳炎、頭蓋内腫瘍などが原因となって...
糖尿病薬の副作用は何ですか?
タンギオリン錠は、軽度から中程度の糖尿病の治療に使用される中国の特許医薬品です。主な効能は、陰と腎を...
白血病の8つの初期症状は何ですか?
白血病には通常、8 つの特定の初期症状は見られません。疲労感や衰弱、繰り返す感染症、出血傾向、リンパ...
ナテグリニド錠の作用機序は何ですか?
ナテグリニド錠は2型糖尿病の治療に使用される薬剤です。その作用機序と適応症は患者に対する治療効果にと...
てんかんを患っている子供は学校に戻ることができますか?
子どもがてんかん発作を起こした場合、特にてんかん治療薬を服用している子どもの場合、治療のために学校に...
体温が37.2度だと肺炎になる可能性はありますか?
一般的に、患者に他の不快な症状がなく、体調が良好であれば、肺炎に感染していない可能性があります。ただ...
トラゾドン塩酸塩錠の副作用は何ですか?
トラゾドン塩酸塩錠は、さまざまな種類のうつ病、うつ症状を伴う不安障害、薬物中毒者の離脱後の気分障害の...
リウマチ因子とは何か
リウマチ因子は、さまざまな自己免疫疾患によく関連する自己抗体です。数値が上昇すると、シェーグレン症候...
アプリコットは血中脂質の「除去剤」でしょうか?医師のアドバイス:血管を詰まらせたくないなら、これらの果物や野菜をもっと食べましょう
暑い夏の午後、リーおばさんは地域活動センターで友人たちと健康についておしゃべりをしていました。最近、...
橋本病にかかっていても妊娠できますか?
橋本病性甲状腺炎は、一般的には橋本病性甲状腺炎を指します。橋本病性甲状腺炎の患者が妊娠できるかどうか...
胃潰瘍を治療する最良の方法は何ですか?
胃潰瘍の治療には、潰瘍の治癒を促進し、悪化や再発を防ぐための薬物療法、食生活の改善、生活習慣の変更が...