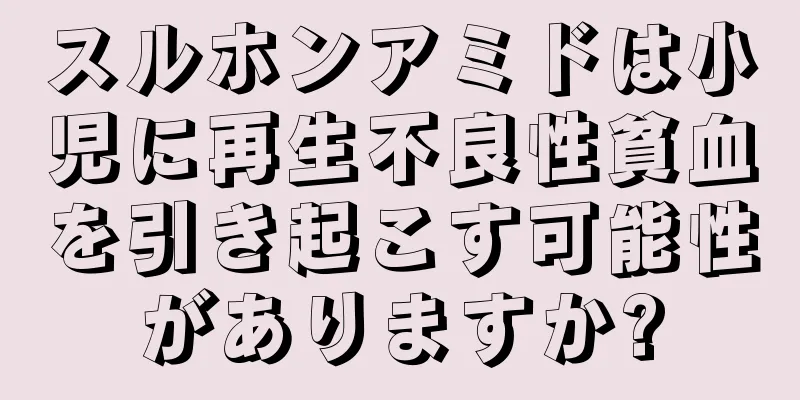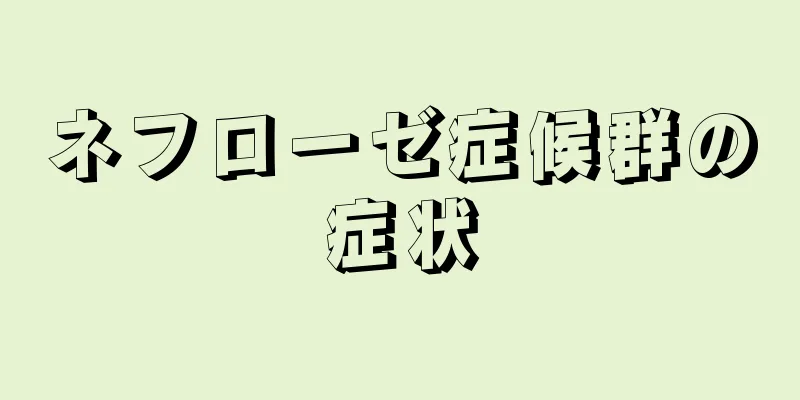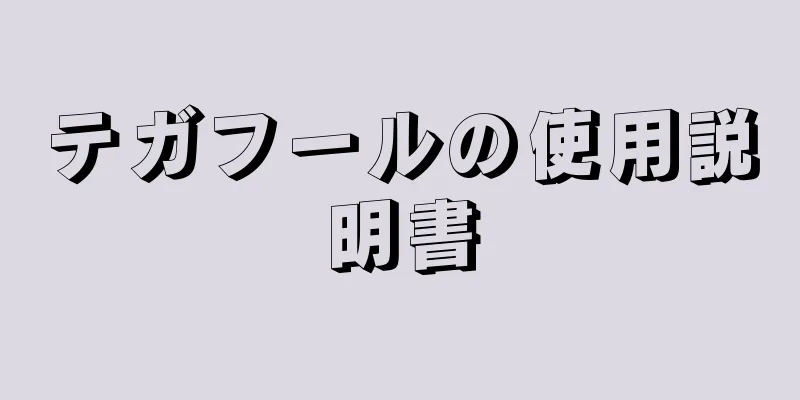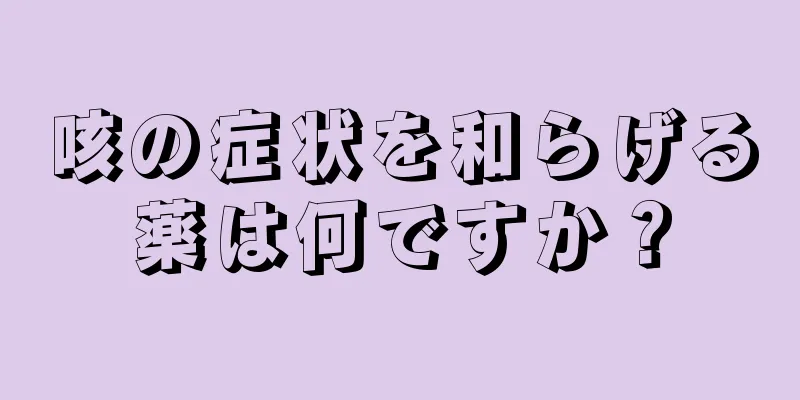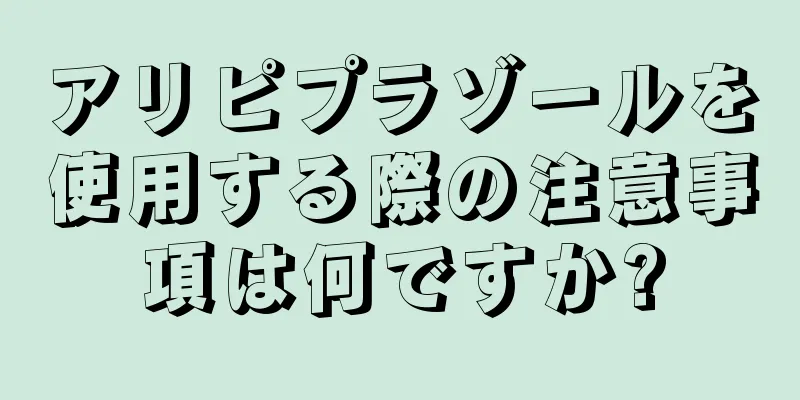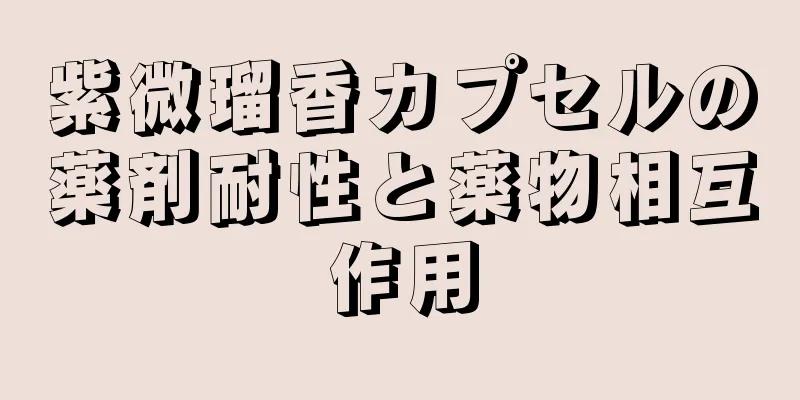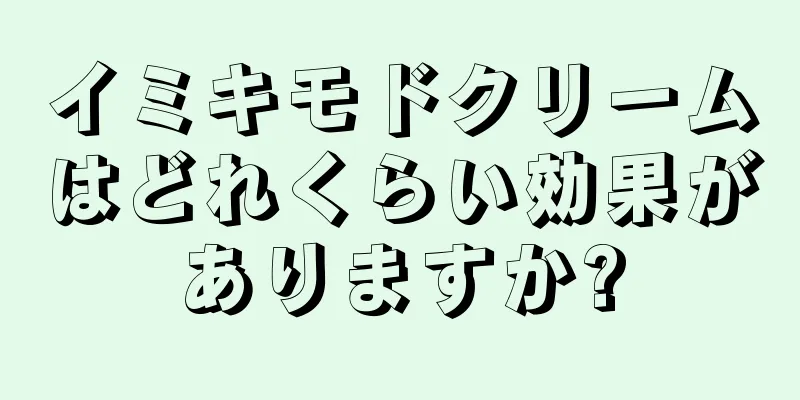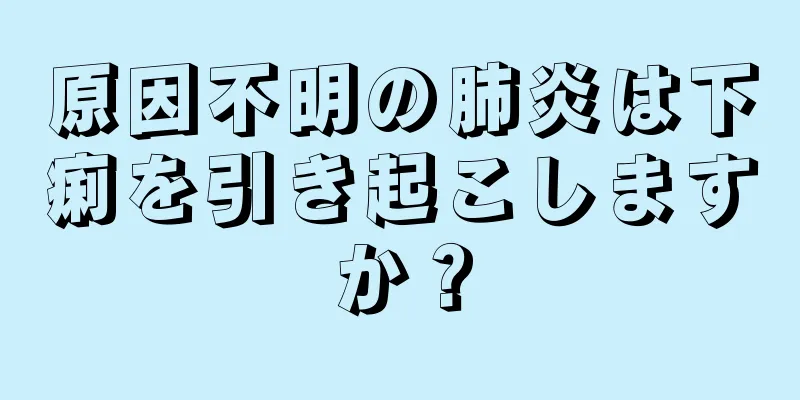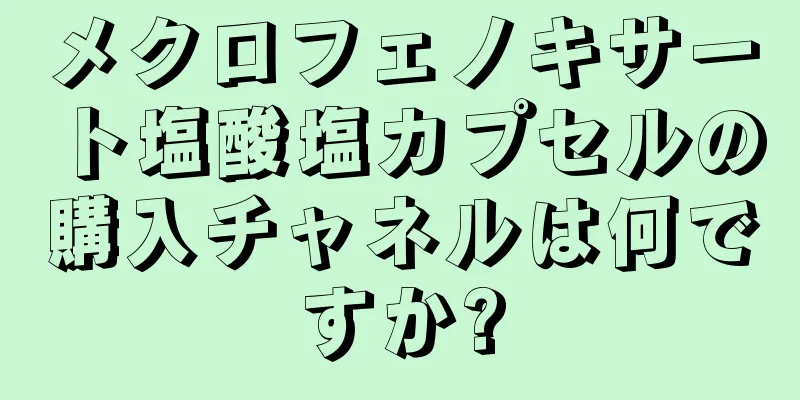アセチルシステインの注意事項と禁忌
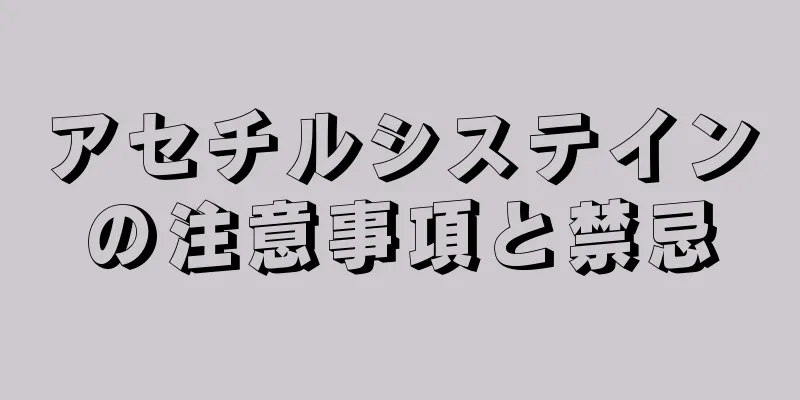
|
アセチルシステインの注意事項と禁忌。アセチルシステインの注意事項は次のとおりです。金属、ゴムなどとの接触を避け、噴霧器はガラスまたはプラスチック製でなければなりません。使用前に溶液を調製し、残りは密閉して冷蔵庫に保管する必要があります。この製品は金製剤の排泄を増加させ、ペニシリン、テトラサイクリンなどの抗菌活性を弱める可能性があるため、これらの薬剤と一緒に使用しないでください。子供は大人の監督下で使用し、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。鎮咳薬と同時に服用しないでください。アンプルを開けると硫黄の臭いがすることがありますが、これは正常です。投薬中は副作用を監視するように注意してください。 アセチルシステインは肝不全の初期治療によく使われる薬です。一定の治療効果はありますが、安全で効果的な治療を確実に行うために、使用時にはいくつかの注意事項と禁忌を考慮する必要があります。 アセチルシステインの注意事項と禁忌は次のとおりです。 1. 適応症の確認 2. 用法・用量 3. 注意事項 4. 禁忌 適応症の確認 アセチルシステインは主に急性酢中毒による急性肝不全や肝障害の治療に使用されます。使用前には、患者が適応症を満たしていること、医師の指導の下で使用していることを確認する必要があります。 用法・用量 アセチルシステインの投与量と使用は、医師のアドバイスに従って厳密に従う必要があります。一般的に、投与量は患者の体重や状態に基づいて決定され、医師の指示に従って定められた時間に定められた量を使用する必要があります。投与量を勝手に増減したり、使用方法を変更したりしないでください。 予防 アセチルシステインを使用する場合、患者は以下の点に注意する必要があります。 1. アレルギー反応に注意してください:患者によってはアセチルシステインにアレルギーを起こす場合があります。発疹、呼吸困難などのアレルギー反応が起こった場合は、直ちに投薬を中止し、医師の診察を受けてください。 2. 腎機能モニタリング:アセチルシステインの代謝経路は腎臓に関係するため、薬剤の安全性を確保するために、使用中は定期的に腎機能をモニタリングする必要があります。 3. 肺疾患の患者には注意して使用してください:重度の肺疾患(気管支炎、喘息など)の患者は、アセチルシステインを使用する際に特に注意する必要があり、必要に応じて綿密な監視が必要です。 禁忌 アセチルシステインは以下の患者には禁忌です: 1. アセチルシステインにアレルギーのある患者。 2. 妊婦は注意して使用してください:アセチルシステインが胎児に与える影響はまだ不明であるため、妊婦は注意して使用するか、医師のアドバイスに従う必要があります。 3. 妊娠:妊娠3ヶ月間はアセチルシステインの摂取を避ける必要があります。 アセチルシステインを使用する場合、患者は医師の指示に厳密に従い、起こりうる副作用に注意し、治療の有効性と患者の安全を確保するために適時に医師の治療を受ける必要があります。 |
推薦する
就寝前に水を飲むと糖尿病患者の血糖値が下がりますか?
就寝前に水を飲むと、糖尿病患者の血糖値が薄まる可能性があります。糖尿病は代謝障害であり、血糖値のコン...
吐き気がしてゲップが出たいのですが出ません。どうしたの?
吐き気やげっぷが出ない原因としては、心理的要因、消化不良、腸の運動低下、逆流性食道炎、胃炎などが考え...
目覚めたときに咳や痰が出るのはなぜですか?
起床時の咳や痰は、環境要因、扁桃炎、咽頭炎、気管支炎、肺炎などの病気に関連している可能性があります。...
ヘリコバクター・ピロリの治療方法
ヘリコバクター・ピロリ菌は、食生活の改善、衛生管理、抗生物質治療、制酸剤、薬剤併用治療などにより改善...
クローン病の一般的な症状
クローン病の最も一般的な症状には、腹痛や下痢、体重減少、疲労、腸閉塞、発熱、全身症状などがあります。...
軽度の心筋炎の5つの初期症状
軽度の心筋炎の初期症状には、疲労感、胸痛、動悸、呼吸困難、風邪の症状などがあります。 1. 疲労: ...
37.3は新型肺炎と言えるのでしょうか?
新型肺炎とは一般的には新型コロナウイルスの感染を指し、37.3℃では新型コロナウイルスの感染とはみな...
顔面神経炎を引き起こすウイルスは何ですか?
顔面神経炎は通常、ウイルス感染によって引き起こされます。最も一般的なウイルスは、水痘帯状疱疹ウイルス...
高齢者が食後に腹部膨満感を感じた場合、どうすればよいでしょうか?高齢者が食後に膨満感を感じる場合、何を食べるべきでしょうか?
食後の胃の膨満感は、消化器官が衰えた高齢者はもちろん、誰にとってもよくある問題です。高齢者の食後のお...
脳血栓症後に狭心症になった場合はどうすればいいですか?
脳血栓症後に狭心症になった場合はどうすればいいですか?脳血栓症後の狭心症では、一般的に、よりよい症状...
化膿し、粘液が滲み出る痛風関節の治療方法
痛風による関節の化膿や粘液の排出は、一般的な治療と薬物療法によって緩和することができます。患者は適時...
糖尿病の初期症状
糖尿病患者は、初期段階では明らかな症状が現れない場合もあれば、食べる量が増える、飲む量が増える、排尿...
敗血症は持続的な微熱を引き起こしますか?
敗血症は、細菌や細菌が作り出す毒素が血液中に侵入する重度の細菌感染によって引き起こされる病気です。敗...
関節リウマチの初期症状とその治療法とは
リウマチとは、一般的に関節リウマチを指します。関節リウマチの患者は、病気の初期段階では朝のこわばり、...
民間療法でリウマチを治す方法
リウマチは一般的に、風、寒さ、湿気などの原因によって引き起こされます。漢方薬、理学療法、食事療法で治...