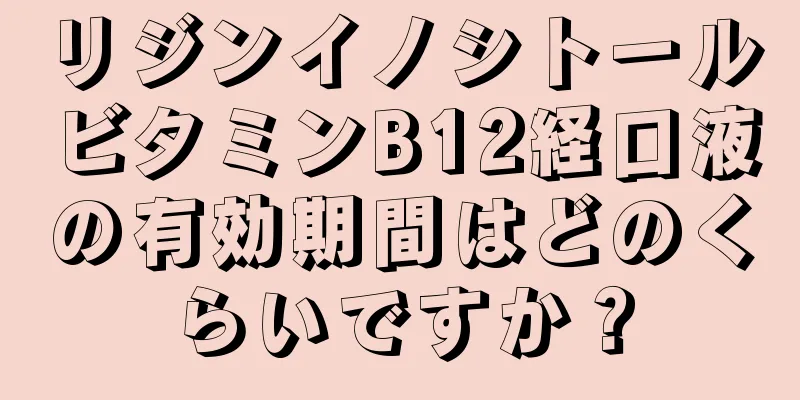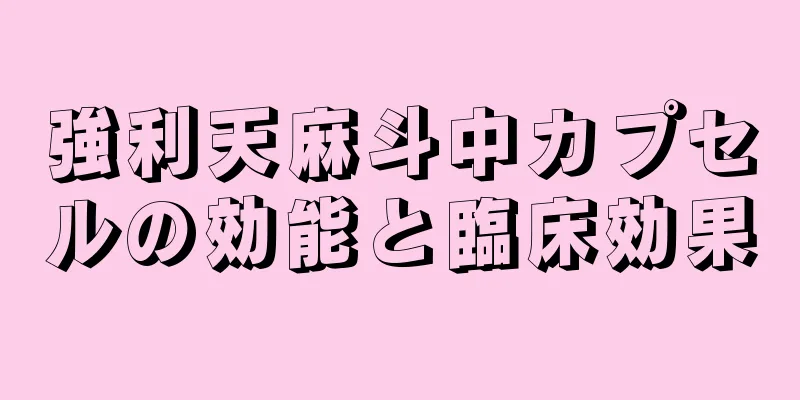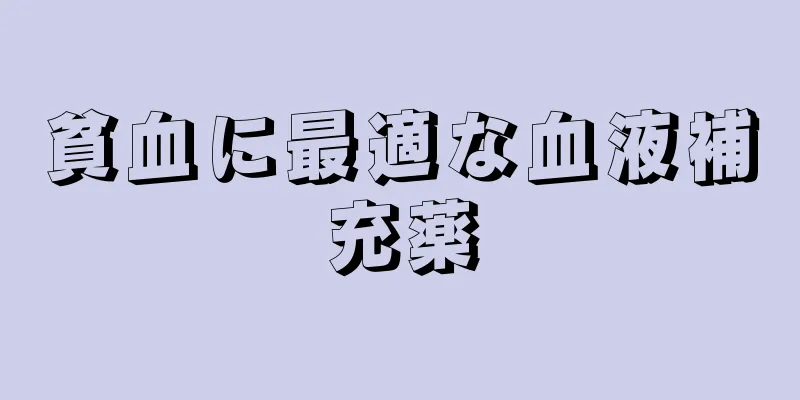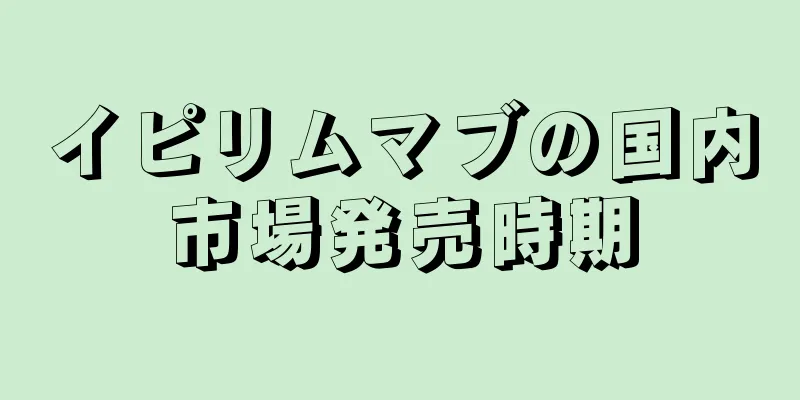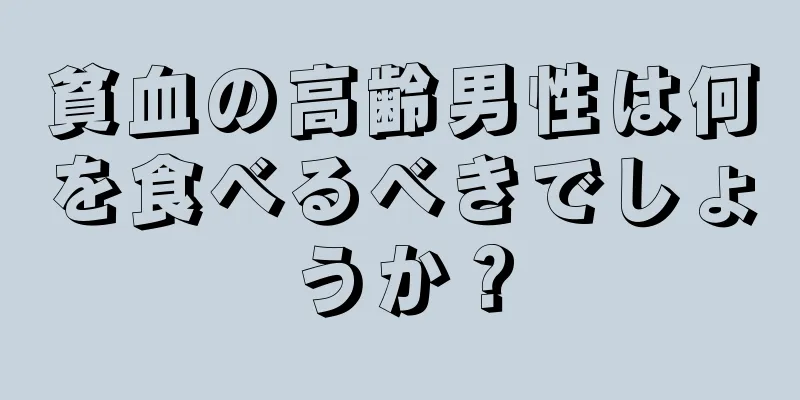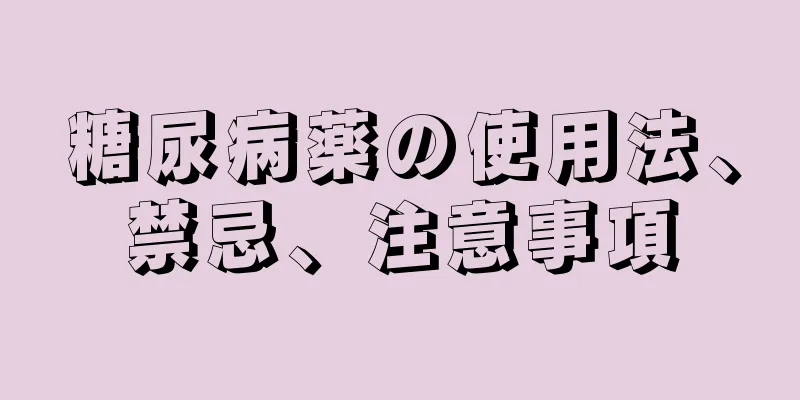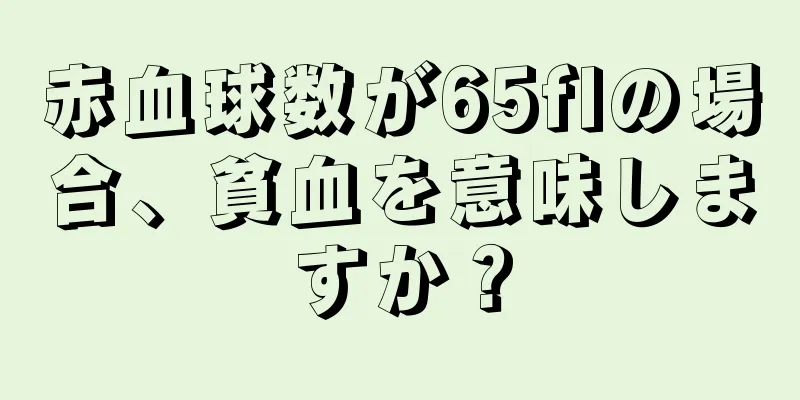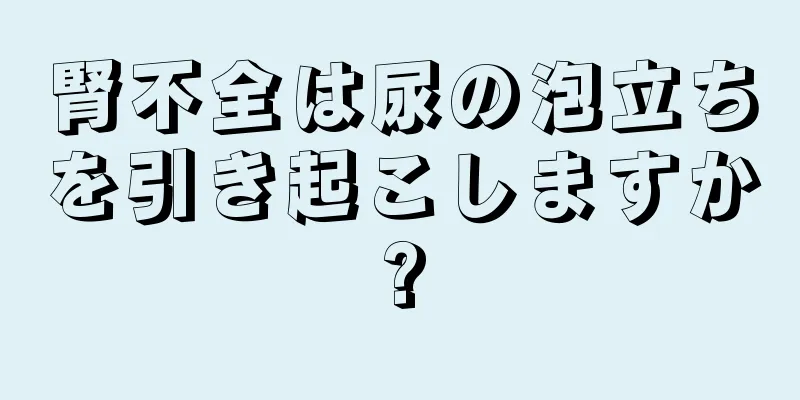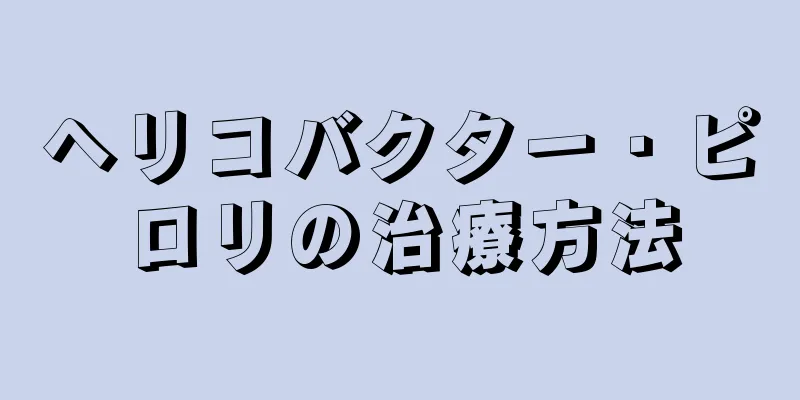小峰智陽顆粒の効能・効果と用量
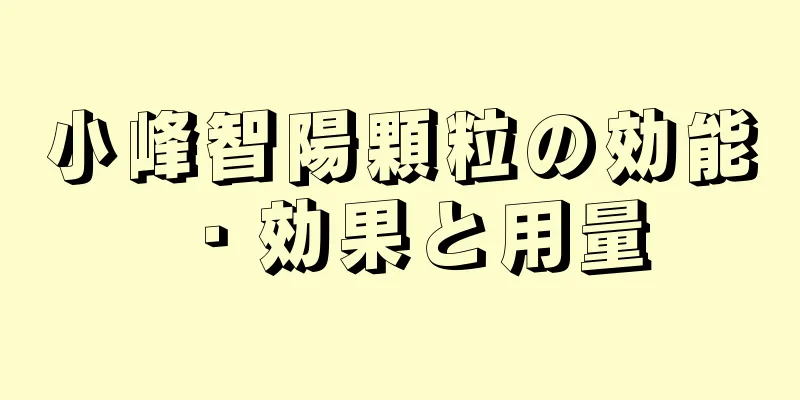
|
小峰芝楊顆粒は伝統的な漢方薬製剤として、さまざまな皮膚疾患、特に丘疹性蕁麻疹、湿疹などによる痒み症状の治療に広く使用されています。その薬効は熱や湿気を取り除き、皮膚の不快感を効果的に和らげることができるため、多くの患者にとって良い選択肢となっています。 1. 丘疹性蕁麻疹の緩和 丘疹性蕁麻疹は、激しいかゆみを伴う、皮膚の赤く盛り上がった斑点として現れることが多い一般的な皮膚疾患です。小風智陽顆粒は風を消し、痒みを和らげる効果があり、この症状を効果的に緩和し、患者が痒みに悩まされることを防ぎます。 2. 湿疹の不快感を和らげる 湿疹は、肘や膝の曲げる部分など、皮膚が擦れ合う部分によく現れる、一般的なタイプの皮膚炎です。湿疹患者は、皮膚の乾燥、赤み、腫れ、かゆみなどの症状に悩まされることが多く、患者にとって大きな悩みの種となっています。小峰芝陽顆粒の清熱・除湿作用は、湿疹による不快感を和らげ、皮膚を健康な状態に戻すのに役立ちます。 3. 皮膚のかゆみを和らげる 小峰智陽顆粒は、丘疹性蕁麻疹や湿疹のほか、その他の皮膚のかゆみ症状の治療にも適しています。アレルギー、湿気、風寒などの原因による皮膚のかゆみも、この薬を使うことで緩和されます。 4. 用法・用量 一般的に、成人は1日3回3〜6グラムを経口摂取し、子供は年齢と体重に応じてより少ない量を摂取します。薬の効能は人によって異なります。服用中は辛い食べ物を避け、個人の衛生に注意し、皮膚を清潔に保つようにしてください。 小鋒智陽顆粒を使用する場合は、医師のアドバイスに従い、副作用に注意し、他の薬との相互作用を避ける必要があります。気分が悪くなったり、症状が悪化した場合は、すぐに医師の診察を受けてください。小峰智陽顆粒は効果はありますが、すべての皮膚疾患に適しているわけではありませんので、使用前には慎重に検討し、医師の指導のもとで使用して、有効性と安全性を確保する必要があります。 |
推薦する
ステージ3高血圧とは何ですか?
ステージ3高血圧とは、患者の高血圧(収縮期血圧)が180 mmHgを超え、低血圧(拡張期血圧)が12...
胃出血の原因は何ですか?
胃出血は、遺伝的要因、環境的要因、生理的要因、外傷、病理学的変化など、さまざまな原因によって引き起こ...
神経痛にはどうすればいいですか?
神経痛にはどうすればいいですか?神経痛性頭痛は、不適切な食生活、悪い生活習慣、悪い姿勢などの原因で引...
日本脳炎の流行を抑制するための効果的な対策は何ですか?
日本脳炎の蔓延を抑制するための効果的な対策としては、感染源の除去、感染経路の遮断、感受性集団の保護な...
冠状動脈疾患の薬を毎日服用すると寿命に影響しますか?
冠状動脈性心疾患は、冠状動脈硬化性心疾患です。冠動脈硬化性心疾患の患者は、通常は病気の治療のために毎...
トブラマイシンはどれくらい効果がありますか?
トブラマイシンはどの程度有効ですか? トブラマイシンは、気管支炎、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎、皮膚および...
ポビドンヨード溶液の中国語説明書
ポビドンヨード溶液は、一般的な局所消毒剤として、医療分野で広く使用されています。化膿性皮膚炎、真菌性...
腎不全患者に適した果物は何ですか?
腎不全の患者は、リンゴ、ナシ、ブルーベリーなど、カリウムやリンの含有量が少ない果物を食べるのが適して...
ポリミキシンBのパッケージ仕様は何ですか?
ポリミキシン B のパッケージ仕様は何ですか? ポリミキシン B の仕様は、50 mg です。ポリミ...
神霊建皮微顆粒は払い戻しできますか?
神霊建皮微顆粒は、脾臓と胃を補い、湿気を除去し、下痢を止めるために一般的に使用される伝統的な漢方薬の...
消化不良と脾臓や胃の弱さの違いは何ですか?
消化不良と脾胃弱症の違いには、性質、原因、検査方法、症状、治療法などが含まれます。 1. 異なる性質...
酸素は心臓病に良いのでしょうか?
酸素療法は心臓病を患う一部の人に役立ちますが、心臓病を患うすべての人に必要なわけではありません。重要...
小児の胃潰瘍の薬物治療
小児の胃潰瘍は、一般的に、医師の処方に従って、胃酸分泌を抑制し、胃粘膜を保護し、胃腸の運動を促進する...
腎臓嚢胞を効果的に予防するにはどうすればいいですか?
腎臓が人体にとって重要であることは自明です。専門家は、多くの患者は病気を積極的に予防し治療するという...
痛風患者は食生活で何に注意すべきでしょうか?
痛風患者はプリンの摂取量をコントロールし、高脂肪食品の摂取を避け、アルコール摂取を控えるなどする必要...